お見舞い

お見舞いとは、一般的には病気や怪我で入院している人や、災害や事故などで自身又は親族の不幸に見舞われた人を励ますためにする行い、またそのために贈る品物やお金を指します。
病気お見舞いでは、入院や療養中の生活用品や励まし、災害見舞いでは被災された方への支援など、状況に合わせて適切な対応をすることが大切です。
病気や怪我で入院している人のお見舞いである「病気お見舞い」、災害(地震、火災、水害、台風など)に遭われた人への「災害お見舞い」が一般的ですが、その他にも季節の挨拶に当たる「暑中お見舞い」、「残暑お見舞い」、「寒中お見舞い」、さらには、選挙事務所や合宿所などで頑張っている人への「陣中お見舞い」、音楽や演劇などの発表会や公演などの楽屋や控室に届ける「楽屋見舞い」など様々な「お見舞い」があります。
病気見舞い
お見舞いのタイミングと面会時間
入院直後や手術前後は避けて、病状によりますが、入院後4~5日後、手術後2~3日後頃が良いとされています。本人だけでなく、相手家族の都合も含め事前に電話などで確認するのがマナーです。
病室を訪れる際は、病院の面会時間内で、かつ病人が疲れないように15~20分程度、寝たきりの場合はさらに短い時間で済ませます。

お見舞いの言葉
病状を詳しく尋ねることは避け、元気付けの言葉を添えるのが適切です。

お見舞いの品
喜ばれる品としては、タオル、寝間着、スリッパなどの日用品や、雑誌、本、写真集などが挙げられます。
のし水引
のし紙の水引は紅白の「5本結切のし無し」で、「表書」を「御見舞」「お見舞」、目上の方に贈る場合や、より丁寧に伝えたい場合に「祈御全快」とします。相手の病気や怪我が重篤な場合には、慶事をイメージさせる紅白の水引は避け、白無地の掛け紙を使うほうが無難です。
▼ 続きを読む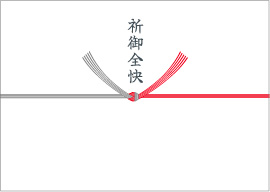
お見舞いに不向きな品
| 病院のルールや 病状を確認する |
花や食べ物は、病院によっては持ち込みを禁止していることがあります。また病状によっても避けた方が良い場合もありますので、事前に病院や親族等に確認をした方が良いでしょう。 |
|---|---|
| 寝具 | 「寝付く」を連想させるため不向きです。 |
| 鉢植えの花 | 寝具同様に「寝付く」を連想させるため不向きです。 |
| 刃物 | 「切る」「分かつ」という縁起が悪い意味があるため、避けます。 |
| 割れるもの | 「割れる」「壊れる」という縁起が悪い意味があるため、避けます。 |
| ハンカチ | 「別れ」を連想させるため、贈るのは避けます。 |
| 櫛 | 「苦」を連想させるため、贈るのは避けます。 |
| 現金・商品券 | すぐに使えないため、お見舞いの品として渡すのは一般的ではありません。 |
| 不向きな花 | ユリや水仙などの香りが強い花や、バラなどの深紅の花、椿や菊などの縁起が悪いとされている花は避けるべきです。 |
相手との関係性によるお見舞品の金額の目安
| 親族 | 5,000円~10,000円 |
|---|---|
| 友人・知人 | 3,000円~5,000円 |
| 職場の上司 | 3,000円~10,000円 |
| 職場の同僚や部下 | 3,000円~5,000円 |
お見舞のお礼、返礼
病気や怪我が快復した時に、退院や回復の報告とともに、お見舞いを頂いた方への感謝の気持ちを伝えるために贈るものです。お礼の品は、頂いたお見舞いの半額から1/3程度の金額を目安に、消え物や洗い流すものが良いとされています。
お菓子、飲み物、フルーツなど、食べたらなくなるもの(消え物)や、病気を後に残さず洗い流すという気持ちを込めて洗剤、石鹸、入浴剤、タオルなどが一般的です。
水引は紅白の5本結切のし無しを使用します。「表書」は「快気祝」「快気内祝」「全快祝」「全快内祝」「快気之内祝」「全快之内祝」など、少し古風な硬い言い方で「本復祝」という「表書」もあります。使い方に差はありません。
またお見舞いを頂いたが当人が亡くなった場合、家族が代わってお礼をする場合がありますが、その際は無地ののし紙に「御見舞御礼」「お見舞いお礼」などとします。

災害お見舞い
災害や火事のお見舞いには、相手の状況に合わせた品物あるいは現金に見舞い状を添えるのが一般的です。被災直後ではなく、ある程度落ち着いてからお見舞いするのが良いでしょう。
▼ 続きを読むお見舞金の目安
被災者の状況によっては、現金が最も役立つ場合があります。5,000円~10,000円程度が相場ですが、関係性によっては高額になることもあります。また、現金ではなく商品券を送るのも良いでしょう。
▼ 続きを読む災害見舞いにおすすめの品
日用品:ライフラインに問題がある、または避難所生活を送っている場合は、飲料水、食料品、寝具、タオルなどの日用品が喜ばれます。ただし、すでに十分な支援を受けている場合もあるため、現場の状況を把握してから贈ります。災害の規模や、相手の状況を把握し、本当に必要なものを贈るようにしましょう。直接被災者に贈るだけでなく、例えば、被災地で必要な物資を集めている団体に寄付するのも良いでしょう。
▼ 続きを読むのしや水引
災害見舞いを送る際の表書は、通常の儀礼贈答ではないので、熨斗や水引のついた熨斗袋は使いません。 災害見舞の場合は白封筒に現金を入れ、「お見舞」「御見舞」「災害御見舞」「震災御見舞」「水害御見舞」「台風御見舞」、火事のお見舞いの場合は、「出火御見舞」「火災御見舞」また、類焼の被害のお見舞いには「近火御見舞」「類焼御見舞」などの表書を書きます。
▼ 続きを読むその他のお見舞い
陣中見舞
楽屋や催事の詰め所、選挙事務所、スポーツの合宿所などにお見舞いを持参する場合に使う「表書」です。 その他の「表書」には、スポーツ・選挙での勝利を願い励ます意味で「祈必勝」「祈御健闘」などがあります。
現金や金券は避け、その場で飲食したり使ったりできる個包装の5千円~1万円ぐらいのお菓子や飲み物などが一般的です。選挙の場合は、「選挙事務所を開いたとき」や「選挙戦たけなわのとき」が持参するタイミングです。水引は紅白の蝶結(花結)を使用します。
楽屋見舞
演劇の公演、音楽コンサートなどで、激励のため楽屋へ持参する場合に使う「表書」です。イベントの最中ではなく準備中の時に持参するのが一般的です。5千円~1万円ぐらいの、簡単につまめるお菓子などの食べ物や飲み物が良いとされ、水引は、紅白の蝶結(花結)を使用します。
▼ 続きを読む御水屋見舞(おみずやみまい)
お茶会に招かれて持参する場合に(ごく親しい人の場合)お茶会を準備した方への感謝の言葉で、お茶会の労苦を労うと共に、感謝の気持ちを表す際の「表書」に使われます。水引は紅白の蝶結(花結)を使います。一般的に1,000円~3,000円程度のお菓子や手土産が選ばれることが多いです。
▼ 続きを読む忌中御見舞
故人が亡くなってから49日目以内(仏教では四十九日忌)に、遺族を訪問し、弔いの気持ちを伝える行為、または「表書」です。やむを得ない事情で通夜や葬儀に参列できなかった場合や、生前にお見舞いに行けなかった場合に、遺族を気遣って訪問する風習です。
忌中見舞いで包む現金には、香典の代わりといった意味も含まれています。黒白または黄白の5本結切のし無しの不祝儀袋(ぶしゅうぎぶくろ)にお金を包んでお渡しするのが一般的です。
【ご友人やお知り合い、会社の方の場合】
5,000円~10,000円前後が目安ですが、生前親しかった方は多めに包む場合もあります。
【叔父・叔母、祖父母などのご親族の場合】
5,000円~10,000円前後が目安です。
【親・兄弟の場合】
10,000~30,000円前後が一般的です。
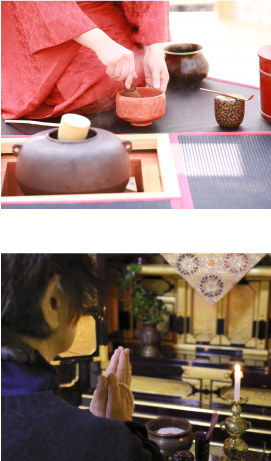
御水屋見舞(おみずやみまい)
お茶会に招かれて持参する場合に(ごく親しい人の場合)お茶会を準備した方への感謝の言葉で、お茶会の労苦を労うと共に、感謝の気持ちを表す際の「表書」に使われます。水引は紅白の蝶結(花結)を使います。一般的に1,000円~3,000円程度のお菓子や手土産が選ばれることが多いです。
▼ 続きを読む
忌中御見舞
故人が亡くなってから49日目以内(仏教では四十九日忌)に、遺族を訪問し、弔いの気持ちを伝える行為、または「表書」です。やむを得ない事情で通夜や葬儀に参列できなかった場合や、生前にお見舞いに行けなかった場合に、遺族を気遣って訪問する風習です。
忌中見舞いで包む現金には、香典の代わりといった意味も含まれています。黒白または黄白の5本結切のし無しの不祝儀袋(ぶしゅうぎぶくろ)にお金を包んでお渡しするのが一般的です。
【ご友人やお知り合い、会社の方の場合】
5,000円~10,000円前後が目安ですが、生前親しかった方は多めに包む場合もあります。
【叔父・叔母、祖父母などのご親族の場合】
5,000円~10,000円前後が目安です。
【親・兄弟の場合】
10,000~30,000円前後が一般的です。

新盆御見舞
「新盆(にいぼん)」とは、故人が亡くなった後(四十九日の忌明け後)に迎える初めてのお盆のことで、「新盆御見舞」はその時に使用する「表書」を指します。故人と親しかった方やご親族は、新盆のご家庭に伺ってお参りをすることで供養の気持ちを伝える風習があり、その際に持参するお供え物を「新盆(初盆)見舞い」と呼びます。不祝儀袋(ぶしゅうぎぶくろ)にお金を包んでお渡しするのが一般的です。
【ご友人やお知り合い、会社の方の場合】
5,000円~10,000円前後が目安ですが、生前親しかった方は多めに包む場合もあります。
【叔父・叔母、祖父母などのご親族の場合】
5,000円~10,000円前後が目安です。
【親・兄弟の場合】
10,000~30,000円前後が一般的です。災害や火事のお見舞いには、相手の状況に合わせた品物あるいは現金に見舞い状を添えるのが一般的です。被災直後ではなく、ある程度落ち着いてからお見舞いするのが良いでしょう。
季節の挨拶(お見舞い)
寒さ・暑さ見舞いの「お見舞い」は、暦の季節で名目が変わります。 立春前は「寒中見舞い」、立秋前は「暑中見舞い」、立秋過ぎは「残暑見舞い」です。 立春はだいたい2月4日、立秋は閏年があると日付がずれて、8月8日または8月7日あたりになります。
季節のお見舞いの目安は3,000~5,000円で、相手との関係性よって金額を変えても問題ありません。 相手が気を遣わず受け取りやすい金額にすることが大切です。のし紙の水引は「紅白の蝶結(花結)」を使用します。
挨拶状を添えることで、より格式高い丁寧な印象を与えられます。挨拶状はギフトが届くタイミングより2~3日前に届くように送るのがおすすめです。挨拶状には、感謝の気持ちや相手の健康を気遣う言葉などを丁寧に書き添えましょう。災害や火事のお見舞いには、相手の状況に合わせた品物あるいは現金に見舞い状を添えるのが一般的です。被災直後ではなく、ある程度落ち着いてからお見舞いするのが良いでしょう。
暑中見舞い
7/15頃までに届く場合は「お中元」、8月初旬の立秋までに届く場合(7/16~8/7頃)は「暑中御見舞い」です。
ただし関西地方では、8/15までは「御中元」で、それ以降に「残暑見舞い」とすることが多いようです。
のし紙の「表書」は、「夏のご挨拶」「暑中御見舞」「暑中お見舞」「暑中お伺い」とします。
暑さが厳しい時期の贈り物なので、冷たいアイスやゼリー、ジュースなど夏に嬉しい品物が人気です。 ご家庭へのギフトならそうめんやハム、オイルなどの調味料が、会社宛なら個包装のお菓子や飲み切りタイプのジュースやコーヒー、日持ちのする焼菓子などが人気です。

残暑お見舞い
8月初旬の立秋までに届く場合(7/16~8/7頃)は「暑中御見舞い」です。
ただし関西地方では、8/15までは「御中元」で、それ以降に「残暑見舞い」とすることが多いようです。
のし紙の「表書」は、「残暑御見舞」「残暑お見舞」「残暑お伺い」とします。
暑中見舞いと同じように、季節感があり暑い時期に嬉しいアイスやゼリー、ジュースなどが人気です。
ご家庭へのギフトならそうめんやハム、オイルなどの調味料、会社宛なら個包装のお菓子や飲み切りタイプのジュースやコーヒー、日持ちのする焼菓子なども喜ばれます。
寒中お見舞い
お歳暮の時期を過ぎてしまった場合、松の内(1月7日頃まで)を過ぎたら、寒中見舞いを贈るのが一般的です。
のし紙の「表書」は、「寒中御見舞」「寒中お見舞」「寒中お伺い」とします。
寒中見舞いの品物は、特に決まりはありませんが、お歳暮とほぼ同じようなものを選びます。定番のギフトとしては、お菓子、お茶、タオル、グルメなどが人気です。また、花やギフト券なども喜ばれます。
「お見舞」という「表書」は
「災害見舞」「病気見舞」の
両方の場合で使用
一般的に病気のお見舞いと、災害お見舞いのどちらでも「お見舞」として使われています。「お見舞」という「表書」。その他の陣中見舞い、水屋見舞い、季節のお見舞い(寒中見舞いなど)の場合は、単なる「お見舞」という「表書」は通常使用しません。
▼ 続きを読む| 表書 | 行事・イベント | 意味 |
|---|---|---|
| お見舞 | 災害見舞 | 災害(地震や台風、水害、火災など)によって被害を受けた人々に対してお見舞いの気持ちを表す際に用います。 支援のために贈られる金品や品物に用いられます。 |
| 病気見舞 | 病気・怪我等で療養している人を見舞い、慰めたり励ましたりするために贈る品物に用いられます。 |
贈り物の基礎知識
暮らしに役立つマナー
生活文化・しきたり百科
歴史から知る現代の冠婚葬祭マナー
冠婚葬祭WEBマナー辞典
- 贈り物の基礎知識
- のし紙・掛紙 マナーガイド
- 失敗しない「ご祝儀」のマナー
- 失敗しない「不祝儀」のマナー
- 暮らしに役立つマナー
- 手紙の書き方・送り方ガイド
- ・手紙の書き方
- ・手紙の送り方のマナー
- ・使えるビジネス文例集
- 神社&お寺での「お祈り」ガイド
- 弔事なんでもガイド
- ・喪家になったときの葬儀ガイド
- ・葬儀に参列するときのマナー
- ・「忌と喪」「法事と法要」について
- お見舞い
- 生活文化・しきたり百科
- 冠婚葬祭
- 年中行事
- 記念日・祝日
- 法人のイベント・行事
- 日本の祭祀・祭礼



 ホーム
ホーム 運営会社
運営会社 サイトマップ
サイトマップ